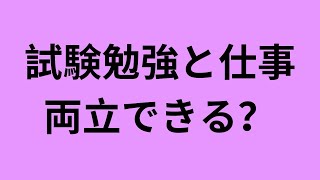ご登録いただくと、続きから問題を
再開する事が出来ます
令和3年 – 問6 – 行政書士 憲法
憲法で、国会が国の「唯一の」立法機関であるとされるのは、憲法自身が定める例外を除き、[ ア ]かつ、[ イ ]を意味すると解されている。
| ア | イ | |
|---|---|---|
| 1 | 内閣の法案提出権を否定し (国会中心立法の原則) |
議員立法の活性化を求めること (国会単独立法の原則) |
| 2 | 国権の最高機関は国会であり (国会中心立法の原則) |
内閣の独立命令は禁止されること (国会単独立法の原則) |
| 3 | 法律は国会の議決のみで成立し (国会単独立法の原則) |
天皇による公布を要しないこと (国会中心立法の原則) |
| 4 | 国会が立法権を独占し (国会中心立法の原則) |
法律は国会の議決のみで成立すること (国会単独立法の原則) |
| 5 | 国権の最高機関は国会であり (国会中心立法の原則) |
立法権の委任は禁止されること (国会単独立法の原則) |
正解4〇×
〔3-6〕
解説
1×
アについて、「国会中心立法の原則」とは、国会が立法権を独占し、国会以外の機関は立法できないことをいう。「立法」とは、法規という特定の内容の法規範を定立することをいう(実質的意味の立法)。「内閣の法案提出」は「立法」ではない。「内閣の法案提出権を否定」することと「国会中心立法の原則」は無関係である。よって、アは誤りである。イについて、「国会単独立法の原則」とは、国会のみが立法の手続を行い、国会以外の機関は参加できないことをいう。「議員立法」とは、議員が法律案を発議して成立した法律をいうが、「議員立法の活性化を求め」ることと、立法手続を国会が独占することは、別の話である。よって、イも誤りである。
2×
アについて、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」(憲41条)。本問は「唯一の」立法機関であるとされることの意味を聞いており、「最高機関」であるかは関係ない。よって、アは誤りである。イについて、「内閣の独立命令は禁止する」のは、「国会中心立法の原則」である。よって、イも誤りである。
3×
アについて、「法律は国会の議決のみで成立」するというのは、「国会単独立法の原則」である。よって、アは正しい。イについて、「公布」とは、成立した法令を国民に周知させるために公示する行為であって「立法」ではない。したがって、「天皇による公布を要しない」ことと「国会中心立法の原則」は無関係である。よって、イは誤りである。
4〇
アについて、「国会が立法権を独占」することは、「国会中心立法の原則」である。よって、アは正しい。イについて、「法律は国会の議決のみで成立すること」は、「国会単独立法の原則」である。よって、イも正しい。○イ「唯一の」の意味は、国会が独占することを意味する。「国会中心立法の原則」は立法(権)の独占。国会単独立法の原則は、立法手続の独占。
5×
アについて、「国権の最高機関は国会であ」ることと「国会中心立法の原則」は無関係である。よって、アは誤りである。イについて、「立法権の委任は禁止され」ていない。憲法に直接の明文規定はないが、「政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることはできない」(憲73条6号但書)と、法律の委任を前提にした規定がある。よって、イは誤りである。
アについて、「国会中心立法の原則」とは、国会が立法権を独占し、国会以外の機関は立法できないことをいう。「立法」とは、法規という特定の内容の法規範を定立することをいう(実質的意味の立法)。「内閣の法案提出」は「立法」ではない。「内閣の法案提出権を否定」することと「国会中心立法の原則」は無関係である。よって、アは誤りである。イについて、「国会単独立法の原則」とは、国会のみが立法の手続を行い、国会以外の機関は参加できないことをいう。「議員立法」とは、議員が法律案を発議して成立した法律をいうが、「議員立法の活性化を求め」ることと、立法手続を国会が独占することは、別の話である。よって、イも誤りである。
2×
アについて、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」(憲41条)。本問は「唯一の」立法機関であるとされることの意味を聞いており、「最高機関」であるかは関係ない。よって、アは誤りである。イについて、「内閣の独立命令は禁止する」のは、「国会中心立法の原則」である。よって、イも誤りである。
3×
アについて、「法律は国会の議決のみで成立」するというのは、「国会単独立法の原則」である。よって、アは正しい。イについて、「公布」とは、成立した法令を国民に周知させるために公示する行為であって「立法」ではない。したがって、「天皇による公布を要しない」ことと「国会中心立法の原則」は無関係である。よって、イは誤りである。
4〇
アについて、「国会が立法権を独占」することは、「国会中心立法の原則」である。よって、アは正しい。イについて、「法律は国会の議決のみで成立すること」は、「国会単独立法の原則」である。よって、イも正しい。○イ「唯一の」の意味は、国会が独占することを意味する。「国会中心立法の原則」は立法(権)の独占。国会単独立法の原則は、立法手続の独占。
5×
アについて、「国権の最高機関は国会であ」ることと「国会中心立法の原則」は無関係である。よって、アは誤りである。イについて、「立法権の委任は禁止され」ていない。憲法に直接の明文規定はないが、「政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることはできない」(憲73条6号但書)と、法律の委任を前提にした規定がある。よって、イは誤りである。
行政書士試験 令和3年度
- 問3 令和3年 憲法
- 問4 令和3年 憲法
- 問5 令和3年 憲法
- 問6 令和3年 憲法
- 問8 令和3年 行政法
- 問9 令和3年 行政法
- 問10 令和3年 行政法
- 問11 令和3年 行政法
- 問12 令和3年 行政法
- 問13 令和3年 行政法
- 問14 令和3年 行政法
- 問15 令和3年 行政法
- 問16 令和3年 行政法
- 問17 令和3年 行政法
- 問18 令和3年 行政法
- 問19 令和3年 行政法
- 問20 令和3年 行政法
- 問21 令和3年 行政法
- 問22 令和3年 行政法
- 問23 令和3年 行政法
- 問24 令和3年 行政法
- 問25 令和3年 行政法
- 問26 令和3年 行政法
- 問27 令和3年 民法
- 問28 令和3年 民法
- 問29 令和3年 民法
- 問30 令和3年 民法
- 問31 令和3年 民法
- 問32 令和3年 民法
- 問33 令和3年 民法
- 問34 令和3年 民法
- 問35 令和3年 民法
- 問36 令和3年 商法
- 問37 令和3年 商法
- 問38 令和3年 商法
- 問39 令和3年 商法
- 問40 令和3年 商法
- 問41 令和3年 多肢選択式 憲法
- 問42 令和3年 多肢選択式 行政法
- 問43 令和3年 多肢選択式 行政法
年度別過去問