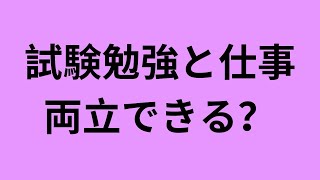ご登録いただくと、続きから問題を
再開する事が出来ます
令和3年 – 問30 – 行政書士 民法
問題30 留置権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものは どれか。
1 留置権者は、善良な管理者の注意をもって留置物を占有すべきであるが、善良な管理者の注意とは、自己の財産に対するのと同一の注意より軽減されたものである。
2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物について使用・賃貸・担保供与をなすことができず、留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を使用した場合、留置権は直ちに消滅する。
3 建物賃借人が賃料不払いにより賃貸借契約を解除された後に当該建物につき有益費を支出した場合、賃貸人による建物明渡請求に対して、賃借人は、有益費償還請求権を被担保債権として当該建物を留置することはできない。
4 Aが自己所有建物をBに売却し登記をB名義にしたものの代金未払のためAが占有を継続していたところ、Bは、同建物をCに転売し、登記は、C名義となった。 Cが所有権に基づき同建物の明渡しを求めた場合、Aは、Bに対する売買代金債権を被担保債権として当該建物を留置することはできない。
5 Dが自己所有建物をEに売却し引渡した後、Fにも同建物を売却しFが所有権移転登記を得た。FがEに対して当該建物の明渡しを求めた場合、Eは、Dに対する履行不能を理由とする損害賠償請求権を被担保債権として当該建物を留置することができる。
正解3〇×
〔3-30〕
解説
1×
留置権者は,善良な管理者の注意を持って留置物を占有する義務(善管注意義務)を負う。留置物は他人の物を占有することにより間接的に債務の弁済を強制する権利である。他人の物を占有している以上,自己の財産に対するのと同一の注意では足りず,それよりも重い義務である善管注意義務が課されている。よって,肢は誤り。
<条文> 298条1項
<判例> -
2×
留置権者は留置物を占有することで債務の弁済を促せるにすぎず,留置物を処分する権原まではない。そのため,留置権者は債務者の承諾なく留置物を使用・賃貸・担保供与できない。しかし,留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を使用しても,留置権はただちに消滅しない。債務者が留置権の消滅を請求して消滅する。よって,肢は誤り。
<条文> 298条3項
<判例> -
3○
物の占有者が,占有物について有益費を支出すれば,所有者に対し費用の償還を求められる。そのため,有益費償還請求権を被担保債権として留置権を行使できそうである。しかし,賃料不払いにより賃貸借契約を解除された後は建物の占有権原がなく,不法占有者となる。不法占有者が留置権を行使して建物の明渡しを拒否するのは当事者間の公平に反する。したがって,「占有が不法行為によって始まった場合には留置権が成立しない」とする295条2項が類推適用され,留置権は成立しない。よって,肢は正しい。
<条文> -
<判例> 最判昭46.7.16
4×
Aは建物をBに売却すると,Bに対し売買代金債権を取得する。AB間の売買契約により,建物はBの所有物となる。Aは「他人の物」である建物を占有し,売買代金債権を被担保債権として,建物を留置できる。よって,肢は誤り。
<条文> -
<判例> 最判昭47.11.16
5×
留置権の被担保債権は,留置物に関して生じた債権である必要がある。EのDに対する履行不能を理由とする損害賠償請求権は,Dに対する所有権移転登記請求権が転化したものである。留置物である建物自体に生じた債権とはいえない。したがって,二重譲渡の場合における損害賠償請求権を理由とする留置権は成立しない。よって,肢は誤り。
<条文> -
<判例> 最判昭43.11.21
留置権者は,善良な管理者の注意を持って留置物を占有する義務(善管注意義務)を負う。留置物は他人の物を占有することにより間接的に債務の弁済を強制する権利である。他人の物を占有している以上,自己の財産に対するのと同一の注意では足りず,それよりも重い義務である善管注意義務が課されている。よって,肢は誤り。
<条文> 298条1項
<判例> -
2×
留置権者は留置物を占有することで債務の弁済を促せるにすぎず,留置物を処分する権原まではない。そのため,留置権者は債務者の承諾なく留置物を使用・賃貸・担保供与できない。しかし,留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を使用しても,留置権はただちに消滅しない。債務者が留置権の消滅を請求して消滅する。よって,肢は誤り。
<条文> 298条3項
<判例> -
3○
物の占有者が,占有物について有益費を支出すれば,所有者に対し費用の償還を求められる。そのため,有益費償還請求権を被担保債権として留置権を行使できそうである。しかし,賃料不払いにより賃貸借契約を解除された後は建物の占有権原がなく,不法占有者となる。不法占有者が留置権を行使して建物の明渡しを拒否するのは当事者間の公平に反する。したがって,「占有が不法行為によって始まった場合には留置権が成立しない」とする295条2項が類推適用され,留置権は成立しない。よって,肢は正しい。
<条文> -
<判例> 最判昭46.7.16
4×
Aは建物をBに売却すると,Bに対し売買代金債権を取得する。AB間の売買契約により,建物はBの所有物となる。Aは「他人の物」である建物を占有し,売買代金債権を被担保債権として,建物を留置できる。よって,肢は誤り。
<条文> -
<判例> 最判昭47.11.16
5×
留置権の被担保債権は,留置物に関して生じた債権である必要がある。EのDに対する履行不能を理由とする損害賠償請求権は,Dに対する所有権移転登記請求権が転化したものである。留置物である建物自体に生じた債権とはいえない。したがって,二重譲渡の場合における損害賠償請求権を理由とする留置権は成立しない。よって,肢は誤り。
<条文> -
<判例> 最判昭43.11.21
行政書士試験 令和3年度
- 問3 令和3年 憲法
- 問4 令和3年 憲法
- 問5 令和3年 憲法
- 問6 令和3年 憲法
- 問8 令和3年 行政法
- 問9 令和3年 行政法
- 問10 令和3年 行政法
- 問11 令和3年 行政法
- 問12 令和3年 行政法
- 問13 令和3年 行政法
- 問14 令和3年 行政法
- 問15 令和3年 行政法
- 問16 令和3年 行政法
- 問17 令和3年 行政法
- 問18 令和3年 行政法
- 問19 令和3年 行政法
- 問20 令和3年 行政法
- 問21 令和3年 行政法
- 問22 令和3年 行政法
- 問23 令和3年 行政法
- 問24 令和3年 行政法
- 問25 令和3年 行政法
- 問26 令和3年 行政法
- 問27 令和3年 民法
- 問28 令和3年 民法
- 問29 令和3年 民法
- 問30 令和3年 民法
- 問31 令和3年 民法
- 問32 令和3年 民法
- 問33 令和3年 民法
- 問34 令和3年 民法
- 問35 令和3年 民法
- 問36 令和3年 商法
- 問37 令和3年 商法
- 問38 令和3年 商法
- 問39 令和3年 商法
- 問40 令和3年 商法
- 問41 令和3年 多肢選択式 憲法
- 問42 令和3年 多肢選択式 行政法
- 問43 令和3年 多肢選択式 行政法
年度別過去問