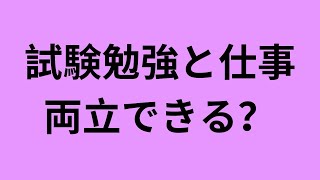ご登録いただくと、続きから問題を
再開する事が出来ます
令和3年 – 問20 – 行政書士 行政法
問題20 次の文章は、消防署の職員が出火の残り火の点検を怠ったことに起因して再出火 した場合において、それにより損害を被ったと主張する者から提起された国家賠償請求訴訟にかかる最高裁判所の判決の一節である。空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。
失火責任法は、失火者の責任条件について民法 709 条[ ア ]を規定したものであるから、国家賠償法 4 条の「民法」に[ イ ]と解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の適用を[ ウ ]合理的理由も存しない。したがって、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法 4 条により失火責任法が[ エ ]され、当該公務員に重大な過失のあることを[ オ ]ものといわなければならない。
(最二小判昭和 53年7月 17 日民集 32巻5号 1000 頁)
| ア | イ | ウ | エ | オ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | の特則 | 含まれる | 排除すべき | 適用 | 必要とする |
| 2 | が適用されないこと | 含まれない | 認めるべき | 排除 | 必要としない |
| 3 | が適用されないこと | 含まれない | 排除すべき | 適用 | 必要としない |
| 4 | が適用されないこと | 含まれる | 認めるべき | 排除 | 必要とする |
| 5 | の特則 | 含まれない | 排除すべき | 適用 | 必要としない |
正解1〇×
〔3-20〕
解説
【完成文】
失火責任法は、失火者の責任条件について民法709条[ア.の特則]を規定したものであるから、国家賠償法4条の「民法」に[イ.含まれる]と解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の適用を[ウ.排除すべき]合理的理由も存しない。したがって、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条により失火責任法が[エ.適用]され、当該公務員に重大な過失のあることを [オ.必要とする]ものといわなければならない。
(最二小判昭和53年7月17日民集32巻5号1000頁)
ア
アには、「の特則」が入る。「失火責任法」とは、失火者の賠償責任を故意・重過失の場合に限定する法律である。本来、民法の不法行為責任は、行為者の故意・過失が責任条件とされる。しかし、失火の場合は、通常の過失(軽過失)しかなければ、賠償責任が否定される。このように、「失火責任法」は、失火について民法に優先適用される特別法であるから、民法709条の特則にあたる。
イ
イには、「含まれる」が入る。国家賠償法4条は、「国または公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による」と定める。「失火責任法」は独立した法律であり、「民法」とは区別されるから、民法に含まれないとするのが筋である。しかし、国家賠償法4条の趣旨は、前三条で規定した事項以外は、民法と同じ扱いをする点にある。よって、国家賠償法がいう「民法」には、民法の附属法規である「失火責任法」も含まれると解釈する。
ウ
ウには、「排除すべき」が入る。「失火責任法」は、①失火者は相当の注意を払っているのが通常で酌量の余地があること②木造家屋が多い日本では類焼による被害が大きく失火者が賠償責任に耐えられないこと③日本には失火者免責の慣習があることを理由に、責任の制限を認める。これらの事情は、「公務員」と私人で変わるところはないから、「公務員」にも「失火責任法」を適用すべきである。よって、「公務員」を「排除すべき」合理的理由はない。
エ
エには、「適用」が入る。「公務員の失火による国または公共団体の損賠賠償責任について、国家賠償法4条により失火責任法が適用され」る。「国又は公共団体」は税金で運営されているので、過度な賠償責任を負わせるべきでない。よって、「失火責任法」を適用するのが妥当である。
オ
オには、「必要とする」が入る。「公務員の失火による」賠償責任については、「公務員」に「重大な過失があること」が要件となる。「失火責任法」が適用されることによる帰結である。
失火責任法は、失火者の責任条件について民法709条[ア.の特則]を規定したものであるから、国家賠償法4条の「民法」に[イ.含まれる]と解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の適用を[ウ.排除すべき]合理的理由も存しない。したがって、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条により失火責任法が[エ.適用]され、当該公務員に重大な過失のあることを [オ.必要とする]ものといわなければならない。
(最二小判昭和53年7月17日民集32巻5号1000頁)
ア
アには、「の特則」が入る。「失火責任法」とは、失火者の賠償責任を故意・重過失の場合に限定する法律である。本来、民法の不法行為責任は、行為者の故意・過失が責任条件とされる。しかし、失火の場合は、通常の過失(軽過失)しかなければ、賠償責任が否定される。このように、「失火責任法」は、失火について民法に優先適用される特別法であるから、民法709条の特則にあたる。
イ
イには、「含まれる」が入る。国家賠償法4条は、「国または公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による」と定める。「失火責任法」は独立した法律であり、「民法」とは区別されるから、民法に含まれないとするのが筋である。しかし、国家賠償法4条の趣旨は、前三条で規定した事項以外は、民法と同じ扱いをする点にある。よって、国家賠償法がいう「民法」には、民法の附属法規である「失火責任法」も含まれると解釈する。
ウ
ウには、「排除すべき」が入る。「失火責任法」は、①失火者は相当の注意を払っているのが通常で酌量の余地があること②木造家屋が多い日本では類焼による被害が大きく失火者が賠償責任に耐えられないこと③日本には失火者免責の慣習があることを理由に、責任の制限を認める。これらの事情は、「公務員」と私人で変わるところはないから、「公務員」にも「失火責任法」を適用すべきである。よって、「公務員」を「排除すべき」合理的理由はない。
エ
エには、「適用」が入る。「公務員の失火による国または公共団体の損賠賠償責任について、国家賠償法4条により失火責任法が適用され」る。「国又は公共団体」は税金で運営されているので、過度な賠償責任を負わせるべきでない。よって、「失火責任法」を適用するのが妥当である。
オ
オには、「必要とする」が入る。「公務員の失火による」賠償責任については、「公務員」に「重大な過失があること」が要件となる。「失火責任法」が適用されることによる帰結である。
行政書士試験 令和3年度
- 問3 令和3年 憲法
- 問4 令和3年 憲法
- 問5 令和3年 憲法
- 問6 令和3年 憲法
- 問8 令和3年 行政法
- 問9 令和3年 行政法
- 問10 令和3年 行政法
- 問11 令和3年 行政法
- 問12 令和3年 行政法
- 問13 令和3年 行政法
- 問14 令和3年 行政法
- 問15 令和3年 行政法
- 問16 令和3年 行政法
- 問17 令和3年 行政法
- 問18 令和3年 行政法
- 問19 令和3年 行政法
- 問20 令和3年 行政法
- 問21 令和3年 行政法
- 問22 令和3年 行政法
- 問23 令和3年 行政法
- 問24 令和3年 行政法
- 問25 令和3年 行政法
- 問26 令和3年 行政法
- 問27 令和3年 民法
- 問28 令和3年 民法
- 問29 令和3年 民法
- 問30 令和3年 民法
- 問31 令和3年 民法
- 問32 令和3年 民法
- 問33 令和3年 民法
- 問34 令和3年 民法
- 問35 令和3年 民法
- 問36 令和3年 商法
- 問37 令和3年 商法
- 問38 令和3年 商法
- 問39 令和3年 商法
- 問40 令和3年 商法
- 問41 令和3年 多肢選択式 憲法
- 問42 令和3年 多肢選択式 行政法
- 問43 令和3年 多肢選択式 行政法
年度別過去問