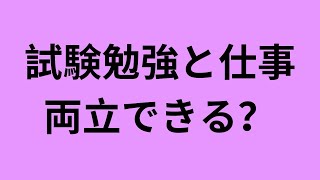ご登録いただくと、続きから問題を
再開する事が出来ます
令和2年 – 問7 – 行政書士 憲法
問題 7 憲法訴訟における違憲性の主張適格が問題となった第三者没収に関する最高裁判所判決*について、次のア~オの記述のうち、法廷意見の見解として、正しいものをすべて挙げた組合せはどれか。
ア 第三者の所有物の没収は、所有物を没収される第三者にも告知、弁解、防禦の機会を与えることが必要であり、これなしに没収することは、適正な法律手続によらないで財産権を侵害することになる。
イ かかる没収の言渡を受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合であっても、それが被告人に対する附加刑である以上、没収の裁判の違憲を理由として上告をすることができる。
ウ 被告人としても、その物の占有権を剥奪され、これを使用・収益できない状態におかれ、所有権を剥奪された第三者から賠償請求権等を行使される危険に曝される等、利害関係を有することが明らかであるから、上告により救済を求めることができるものと解すべきである。
エ 被告人自身は本件没収によって現実の具体的不利益を蒙ってはいないから、現実の具体的不利益を蒙っていない被告人の申立に基づき没収の違憲性に判断を加えることは、将来を予想した抽象的判断を下すものに外ならず、憲法 81 条が付与する違憲審査権の範囲を逸脱する。
オ 刑事訴訟法では、被告人に対して言い渡される判決の直接の効力が被告人以外の第三者に及ぶことは認められていない以上、本件の没収の裁判によって第三者の所有権は侵害されていない。
(注) * 最大判昭和 37 年 11 月 28 日刑集 16 巻 11 号 1593 頁
1 ア・イ
2 ア・エ
3 イ・オ
4 ア・イ・ウ
5 ア・エ・オ
正解エ:オ〇×
〔2-7〕
解説
ア○
「第三者の所有物の没収」があったとしても、第三者は訴訟当事者ではない。違憲の主張はできないとするのが筋である。しかし、主張できないとすると、第三者は、「適正な法律手続きによらないで財産権を侵害」されることになる。適正手続の保障(憲31条)に反する。そこで、「第三者の所有権の没収」に際して、「所有物を没収される第三者にも告知、弁解、防禦の機会を与えることが必要で」ある。
イ○
「かかる没収の言渡しを受けた被告人は」、没収されるものは「第三者の所有物」である。自己の財産権に対する直接の侵害はなく手続的保障は不要ではないか。しかし、「たとえ第三者の所有物に関する場合であっても」、それが被告人に対する附加刑(死刑、懲役、禁錮というような主刑に付加される、所有権を剥奪される没収の刑をいう)である。そのため、その物の占有権を剥奪され、使用・収益できなくなる等、間接的な自己の財産への侵害がある。「没収の裁判の違憲を理由として上告をすることが」できると、すべきである。
ウ○
「被告人としても、その物の占有権を剥奪され、これを使用・収益できない状態におかれ、所有権を剥奪された第三者から賠償請求等を行使される危険に曝される等、利害関係を有することは明らかである」したがって、被告人自身に第三者の所有物没収の主張適格が認められる。「上告により救済を求めることができるものと解すべきである」。
エ×
「被告人自身は本件没収によって現実の具体的不利益を蒙ってはいない」。だが、「現実の具体的不利益を 蒙ってはいない被告人の申立に基づき没収の違憲性に判断を加えることは、将来を予想した抽象的判断 を下す」ものではない。被告人としても、その物の占有権を剥奪され、これを使用・収益できない状態 におかれる。「たとえ第三者の所有物に関する場合であっても」、その物の占有権を剥奪され、使用・ 収益できなくなる等、間接的な自己の財産への侵害がある。肢は、第三者の没収に対して、第三者ばか りでなく本人にも違憲性の主張適格を認めた「法廷意見」の見解としては、誤りである。
オ×
「第三者の所有物の没収は、被告人に対する付加刑として言い渡され、その刑事処分の効果が(第三者の当該物の所有権の剥奪等)第三者に及ぶものであるから・・・財産権を侵害する制裁を科するに他ならない」(最大判昭37.11.28)。「刑事訴訟法では、被告人に対して言い渡される判決の直接の効力が被告人以外の第三者に及ぶ」場合がある。したがって、「裁判によって第三者の所有権は侵害されない」とするのは、判決の直接の効力が第三者にも及ぶとする「法廷意見」の見解としては、誤りである。
「第三者の所有物の没収」があったとしても、第三者は訴訟当事者ではない。違憲の主張はできないとするのが筋である。しかし、主張できないとすると、第三者は、「適正な法律手続きによらないで財産権を侵害」されることになる。適正手続の保障(憲31条)に反する。そこで、「第三者の所有権の没収」に際して、「所有物を没収される第三者にも告知、弁解、防禦の機会を与えることが必要で」ある。
イ○
「かかる没収の言渡しを受けた被告人は」、没収されるものは「第三者の所有物」である。自己の財産権に対する直接の侵害はなく手続的保障は不要ではないか。しかし、「たとえ第三者の所有物に関する場合であっても」、それが被告人に対する附加刑(死刑、懲役、禁錮というような主刑に付加される、所有権を剥奪される没収の刑をいう)である。そのため、その物の占有権を剥奪され、使用・収益できなくなる等、間接的な自己の財産への侵害がある。「没収の裁判の違憲を理由として上告をすることが」できると、すべきである。
ウ○
「被告人としても、その物の占有権を剥奪され、これを使用・収益できない状態におかれ、所有権を剥奪された第三者から賠償請求等を行使される危険に曝される等、利害関係を有することは明らかである」したがって、被告人自身に第三者の所有物没収の主張適格が認められる。「上告により救済を求めることができるものと解すべきである」。
エ×
「被告人自身は本件没収によって現実の具体的不利益を蒙ってはいない」。だが、「現実の具体的不利益を 蒙ってはいない被告人の申立に基づき没収の違憲性に判断を加えることは、将来を予想した抽象的判断 を下す」ものではない。被告人としても、その物の占有権を剥奪され、これを使用・収益できない状態 におかれる。「たとえ第三者の所有物に関する場合であっても」、その物の占有権を剥奪され、使用・ 収益できなくなる等、間接的な自己の財産への侵害がある。肢は、第三者の没収に対して、第三者ばか りでなく本人にも違憲性の主張適格を認めた「法廷意見」の見解としては、誤りである。
オ×
「第三者の所有物の没収は、被告人に対する付加刑として言い渡され、その刑事処分の効果が(第三者の当該物の所有権の剥奪等)第三者に及ぶものであるから・・・財産権を侵害する制裁を科するに他ならない」(最大判昭37.11.28)。「刑事訴訟法では、被告人に対して言い渡される判決の直接の効力が被告人以外の第三者に及ぶ」場合がある。したがって、「裁判によって第三者の所有権は侵害されない」とするのは、判決の直接の効力が第三者にも及ぶとする「法廷意見」の見解としては、誤りである。
行政書士試験 令和2年度
- 問3 令和2年 憲法
- 問4 令和2年 憲法
- 問6 令和2年 憲法
- 問7 令和2年 憲法
- 問8 令和2年 行政法
- 問9 令和2年 行政法
- 問10 令和2年 行政法
- 問11 令和2年 行政法
- 問12 令和2年 行政法
- 問13 令和2年 行政法
- 問14 令和2年 行政法
- 問15 令和2年 行政法
- 問16 令和2年 行政法
- 問17 令和2年 行政法
- 問18 令和2年 行政法
- 問19 令和2年 行政法
- 問20 令和2年 行政法
- 問21 令和2年 行政法
- 問22 令和2年 行政法
- 問23 令和2年 行政法
- 問24 令和2年 行政法
- 問25 令和2年 行政法
- 問26 令和2年 行政法
- 問27 令和2年 民法
- 問28 令和2年 民法
- 問29 令和2年 民法
- 問30 令和2年 民法
- 問31 令和2年 民法
- 問32 令和2年 民法
- 問33 令和2年 民法
- 問34 令和2年 民法
- 問35 令和2年 民法
- 問36 令和2年 商法
- 問37 令和2年 商法
- 問38 令和2年 商法
- 問39 令和2年 商法
- 問40 令和2年 商法
- 問41 令和2年 多肢選択式 憲法
- 問42 令和2年 多肢選択式 行政法
- 問43 令和2年 多肢選択式 行政法
年度別過去問