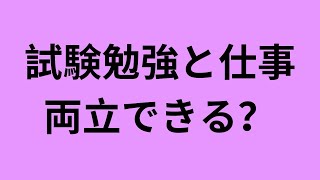ご登録いただくと、続きから問題を
再開する事が出来ます
令和2年 – 問30 – 行政書士 民法
問題30 A・B間において、Aが、Bに対して、Aの所有する甲建物または乙建物のうちいずれかを売買する旨の契約が締結された。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。
1 給付の目的を甲建物とするか乙建物とするかについての選択権は、A・B間に特約がない場合には、Bに帰属する。
2 A・B間の特約によってAが選択権者となった場合に、Aは、給付の目的物として甲建物を選択する旨の意思表示をBに対してした後であっても、Bの承諾を得ることなく、その意思表示を撤回して、乙建物を選択することができる。
3 A・B間の特約によってAが選択権者となった場合において、Aの過失によって甲建物が焼失したためにその給付が不能となったときは、給付の目的物は、乙建物になる。
4 A・B間の特約によって第三者Cが選択権者となった場合において、Cの選択権の行使は、AおよびBの両者に対する意思表示によってしなければならない。
5 A・B間の特約によって第三者Cが選択権者となった場合において、Cが選択をすることができないときは、選択権は、Bに移転する。
正解3〇×
〔2-30〕
解説
1×
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まる場合(選択債権)、原則として、債務者が選択権を持つ。給付義務を負担する者が選択するのが公平だからである。本肢でも、給付の目的物が甲建物か乙建物かについての選択権は、A・B間に特約がなければ、債務者Aに帰属する。よって、肢は誤り。
<条文> 406条
<判例> -
2×
選択権の行使は、相手方に対する意思表示によって行う。相手は選択権者の意思表示を信頼して行動する。この信頼を保護するため、一度行われた選択権の行使は、相手方の承諾がなければ撤回できない。本肢でも、Aが、給付の目的物を甲建物から乙建物を選択する場合には、Bの承諾を得る必要がある。よって、肢は誤り。
<条文> 407条2項
<判例> -
3○
選択権をもつ当事者の過失が原因で目的物が不能となった場合、公平の観点から不能の原因を作った者は選択権を失う。また、選択債権の対象となる複数の給付は、通常、同価値だから、残存する方に給付を特定しても、当事者に不都合はない。したがって、選択権者Aの過失によって甲建物が滅失した場合には、給付の目的物は乙建物となる。よって、肢は正しい。
<条文> 410条
<判例> -
4×
選択債権における選択権は、特約によって第三者に選択権を帰属させることもできる。そして、第三者が選択権を行使するには、債権者または債務者に意思表示をすればよく、両者に対し意思表示する必要はない。一方に意思表示すれば、他方に連絡が行くと期待できる。本肢でも、第三者Cは、AまたはBのどちらかに意思表示すればよい。よって、肢は誤り。
<条文> 409条1項
<判例> -
5×
選択債権では、原則として、給付の義務を負担する債務者が選択権を有する。他方、契約の当事者は第三者を選択権者にできる。第三者が選択できない場合、選択権は原則に戻り、債務者に帰属する。したがって、第三者Cが選択できない時は、選択権は債務者Aに移転する。よって、肢は誤り。
<条文> 409条2項
<判例> -
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まる場合(選択債権)、原則として、債務者が選択権を持つ。給付義務を負担する者が選択するのが公平だからである。本肢でも、給付の目的物が甲建物か乙建物かについての選択権は、A・B間に特約がなければ、債務者Aに帰属する。よって、肢は誤り。
<条文> 406条
<判例> -
2×
選択権の行使は、相手方に対する意思表示によって行う。相手は選択権者の意思表示を信頼して行動する。この信頼を保護するため、一度行われた選択権の行使は、相手方の承諾がなければ撤回できない。本肢でも、Aが、給付の目的物を甲建物から乙建物を選択する場合には、Bの承諾を得る必要がある。よって、肢は誤り。
<条文> 407条2項
<判例> -
3○
選択権をもつ当事者の過失が原因で目的物が不能となった場合、公平の観点から不能の原因を作った者は選択権を失う。また、選択債権の対象となる複数の給付は、通常、同価値だから、残存する方に給付を特定しても、当事者に不都合はない。したがって、選択権者Aの過失によって甲建物が滅失した場合には、給付の目的物は乙建物となる。よって、肢は正しい。
<条文> 410条
<判例> -
4×
選択債権における選択権は、特約によって第三者に選択権を帰属させることもできる。そして、第三者が選択権を行使するには、債権者または債務者に意思表示をすればよく、両者に対し意思表示する必要はない。一方に意思表示すれば、他方に連絡が行くと期待できる。本肢でも、第三者Cは、AまたはBのどちらかに意思表示すればよい。よって、肢は誤り。
<条文> 409条1項
<判例> -
5×
選択債権では、原則として、給付の義務を負担する債務者が選択権を有する。他方、契約の当事者は第三者を選択権者にできる。第三者が選択できない場合、選択権は原則に戻り、債務者に帰属する。したがって、第三者Cが選択できない時は、選択権は債務者Aに移転する。よって、肢は誤り。
<条文> 409条2項
<判例> -
行政書士試験 令和2年度
- 問3 令和2年 憲法
- 問4 令和2年 憲法
- 問6 令和2年 憲法
- 問7 令和2年 憲法
- 問8 令和2年 行政法
- 問9 令和2年 行政法
- 問10 令和2年 行政法
- 問11 令和2年 行政法
- 問12 令和2年 行政法
- 問13 令和2年 行政法
- 問14 令和2年 行政法
- 問15 令和2年 行政法
- 問16 令和2年 行政法
- 問17 令和2年 行政法
- 問18 令和2年 行政法
- 問19 令和2年 行政法
- 問20 令和2年 行政法
- 問21 令和2年 行政法
- 問22 令和2年 行政法
- 問23 令和2年 行政法
- 問24 令和2年 行政法
- 問25 令和2年 行政法
- 問26 令和2年 行政法
- 問27 令和2年 民法
- 問28 令和2年 民法
- 問29 令和2年 民法
- 問30 令和2年 民法
- 問31 令和2年 民法
- 問32 令和2年 民法
- 問33 令和2年 民法
- 問34 令和2年 民法
- 問35 令和2年 民法
- 問36 令和2年 商法
- 問37 令和2年 商法
- 問38 令和2年 商法
- 問39 令和2年 商法
- 問40 令和2年 商法
- 問41 令和2年 多肢選択式 憲法
- 問42 令和2年 多肢選択式 行政法
- 問43 令和2年 多肢選択式 行政法
年度別過去問