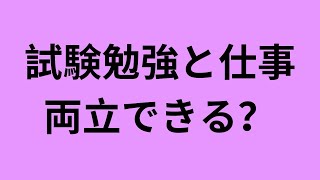ご登録いただくと、続きから問題を
再開する事が出来ます
令和2年 – 問19 – 行政書士 行政法
問題19 行政事件訴訟法が定める義務付け訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはど れか。
1 申請拒否処分がなされた場合における申請型義務付け訴訟は、拒否処分の取消訴訟と併合提起しなければならないが、その無効確認訴訟と併合提起することはできない。
2 行政庁が義務付け判決に従った処分をしない場合には、裁判所は、行政庁に代わって当該処分を行うことができる。
3 義務付け判決には、取消判決の拘束力の規定は準用されているが、第三者効の規定は準用されていない。
4 処分がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある場合には、当該処分につき義務付け訴訟を提起しなくとも、仮の義務付けのみを単独で申し立てることができる。
5 義務付け訴訟は、行政庁の判断を待たず裁判所が一定の処分を義務付けるものであるから、申請型、非申請型のいずれの訴訟も、「重大な損害を生じるおそれ」がある場合のみ提起できる。
正解3〇×
〔2-19〕
解説
1×
「申請拒否処分がなされた場合における申請型義務付け訴訟は」、拒否処分における取消訴訟の併合提起と同様に、無効確認訴訟においても「併合提起することができる」。理由は、「義務付け訴訟」とは、「行政庁が、その処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟」のことをいう(行訴3条6項柱書)。申請型義務付け訴訟と非申請型義務付け訴訟がある。そのうち、申請型義務付け訴訟とは、申請、または審査請求がなされた場合において、当該行政庁が、その処分または裁決をすべきであるにも関わらずこれがなされないときの訴えをいう(行訴3条6項2号)。①申請拒否処分がなされた場合に、紛争の迅速かつ抜本的な解決のため、②(拒否処分の)取消訴訟、または③無効確認訴訟とを「併合提起」することが訴訟要件となっているからである(行訴37条の3第3項2号)。
2×
「行政庁が義務付け判決にしたがった処分をしない場合に、裁判所」が、「行政庁に代わって当該処分を行うこと」はできない。理由は、裁判所は、具体的争訟に法を適用し解決する法原理機関である。法に特別の規定がない限り、行政に立ち入ることはできないからである。事実、そのような法律の規定はない。
3○
「義務付け判決には、取消判決の拘束力の規定は準用されているが、第三者効の規定は準用されていない」。理由は、義務付け訴訟とは、行政庁にその処分又は裁決をすべき旨を命ずる訴訟をいう(行訴3条6項柱書)。訴訟の効果として、既判力(確定判決の後訴における通用力ないし、拘束力)は当然、当事者間では生じさせるべきである(行訴38条1項準用33条1項)。しかし、第三者効(行訴32条1項)まで生ずるとすると、訴訟に参加していない者の法律関係まで影響を与える。不測の損害を生じさせるおそれがあるからである。
4×
「当該処分につき」、たとえ「損害を避けるため緊急の必要」があったとしても、「仮の義務付けのみ を単独で申し立てること」はできない。理由は、「仮の義務付け」とは、あらかじめ義務付けの訴えの 提起がされているが、当該訴訟の結論を待っていては、損害を避けることが間に合わない場合に求める、 非常救済手段だからである(行訴37条の5第1項)。
5×
義務付け訴訟において、申請型、非申請型のいずれも「行政庁の判断を待たず裁判所が一定の処分を義務付けるもの」との指摘は正しい。しかし、「『重大な損害を生じるおそれ』がある場合のみ」に限定して提起することが認められるのは、非申請型のみである。理由は、「非申請型義務付け訴訟」とは、行政庁が、一定の処分をすべきであるにもかかわらず、なされないときにあとから訴える訴訟をいう(行訴3条6項1号)。申請していないにもかかわらず、行政庁に一定の処分を義務付けるため、訴権の濫用のおそれがあるからである(行訴37条の2第1項前半)。
「申請拒否処分がなされた場合における申請型義務付け訴訟は」、拒否処分における取消訴訟の併合提起と同様に、無効確認訴訟においても「併合提起することができる」。理由は、「義務付け訴訟」とは、「行政庁が、その処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟」のことをいう(行訴3条6項柱書)。申請型義務付け訴訟と非申請型義務付け訴訟がある。そのうち、申請型義務付け訴訟とは、申請、または審査請求がなされた場合において、当該行政庁が、その処分または裁決をすべきであるにも関わらずこれがなされないときの訴えをいう(行訴3条6項2号)。①申請拒否処分がなされた場合に、紛争の迅速かつ抜本的な解決のため、②(拒否処分の)取消訴訟、または③無効確認訴訟とを「併合提起」することが訴訟要件となっているからである(行訴37条の3第3項2号)。
2×
「行政庁が義務付け判決にしたがった処分をしない場合に、裁判所」が、「行政庁に代わって当該処分を行うこと」はできない。理由は、裁判所は、具体的争訟に法を適用し解決する法原理機関である。法に特別の規定がない限り、行政に立ち入ることはできないからである。事実、そのような法律の規定はない。
3○
「義務付け判決には、取消判決の拘束力の規定は準用されているが、第三者効の規定は準用されていない」。理由は、義務付け訴訟とは、行政庁にその処分又は裁決をすべき旨を命ずる訴訟をいう(行訴3条6項柱書)。訴訟の効果として、既判力(確定判決の後訴における通用力ないし、拘束力)は当然、当事者間では生じさせるべきである(行訴38条1項準用33条1項)。しかし、第三者効(行訴32条1項)まで生ずるとすると、訴訟に参加していない者の法律関係まで影響を与える。不測の損害を生じさせるおそれがあるからである。
4×
「当該処分につき」、たとえ「損害を避けるため緊急の必要」があったとしても、「仮の義務付けのみ を単独で申し立てること」はできない。理由は、「仮の義務付け」とは、あらかじめ義務付けの訴えの 提起がされているが、当該訴訟の結論を待っていては、損害を避けることが間に合わない場合に求める、 非常救済手段だからである(行訴37条の5第1項)。
5×
義務付け訴訟において、申請型、非申請型のいずれも「行政庁の判断を待たず裁判所が一定の処分を義務付けるもの」との指摘は正しい。しかし、「『重大な損害を生じるおそれ』がある場合のみ」に限定して提起することが認められるのは、非申請型のみである。理由は、「非申請型義務付け訴訟」とは、行政庁が、一定の処分をすべきであるにもかかわらず、なされないときにあとから訴える訴訟をいう(行訴3条6項1号)。申請していないにもかかわらず、行政庁に一定の処分を義務付けるため、訴権の濫用のおそれがあるからである(行訴37条の2第1項前半)。
行政書士試験 令和2年度
- 問3 令和2年 憲法
- 問4 令和2年 憲法
- 問6 令和2年 憲法
- 問7 令和2年 憲法
- 問8 令和2年 行政法
- 問9 令和2年 行政法
- 問10 令和2年 行政法
- 問11 令和2年 行政法
- 問12 令和2年 行政法
- 問13 令和2年 行政法
- 問14 令和2年 行政法
- 問15 令和2年 行政法
- 問16 令和2年 行政法
- 問17 令和2年 行政法
- 問18 令和2年 行政法
- 問19 令和2年 行政法
- 問20 令和2年 行政法
- 問21 令和2年 行政法
- 問22 令和2年 行政法
- 問23 令和2年 行政法
- 問24 令和2年 行政法
- 問25 令和2年 行政法
- 問26 令和2年 行政法
- 問27 令和2年 民法
- 問28 令和2年 民法
- 問29 令和2年 民法
- 問30 令和2年 民法
- 問31 令和2年 民法
- 問32 令和2年 民法
- 問33 令和2年 民法
- 問34 令和2年 民法
- 問35 令和2年 民法
- 問36 令和2年 商法
- 問37 令和2年 商法
- 問38 令和2年 商法
- 問39 令和2年 商法
- 問40 令和2年 商法
- 問41 令和2年 多肢選択式 憲法
- 問42 令和2年 多肢選択式 行政法
- 問43 令和2年 多肢選択式 行政法
年度別過去問