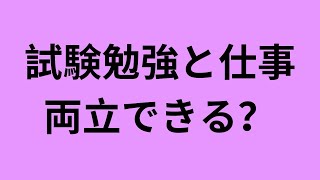ご登録いただくと、続きから問題を
再開する事が出来ます
令和2年 – 問22 – 行政書士 行政法
問題22 住民について定める地方自治法の規定に関する次のア~オの記述のうち、正しい ものの組合せはどれか。
ア 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村およびこれを包括する都道府県の住民とする。
イ 住民は、日本国籍の有無にかかわらず、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
ウ 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
エ 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、その属する普通地方公共団体のすべての条例について、その内容にかかわらず、制定または改廃を請求する権利を有する。
オ 都道府県は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。
1 ア・ウ
2 ア・オ
3 イ・ウ
4 イ・エ
5 エ・オ
正解ア:ウ〇×
〔2-22〕
解説
ア○
市町村の区域内に住んでいる者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民といえる。そこで、地方自治法10条1項は、「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする」と、「住民」を規定している。
イ×
普通地方公共団体の選挙に参与する権利とは、地方公共団体の選挙における選挙権および被選挙権をいう。憲法には、日本国籍を有しない外国人の選挙に参与する権利を認めた規定はない。国民主権(憲1条)から日本国籍を有する者のみ認められるべきである。そこで、地方自治法11条は、「普通地方公共団体の選挙に参与する権利」を「日本国民たる地方公共団体の住民」と、限定している。
ウ○
地方自治とは、日本の地域社会において、住民によって民主的な行政を行うことをいう。住民のための行政である以上、住民は、その役務を享受する権利とともに権利の裏面である義務を負うべきである。そこで、地方自治法10条2項は、「法律の定める所により、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う」としている。
エ×
住民による民主的行政という点からは、「その属する普通地方公共団体のすべての条例について、内容 にかかわらず、制定または改廃を請求する権利を有する」とするのが筋である。しかし、条例には日常 の運営に関する地方税の手数料、使用料等の税金や手続き的な内容のものも含まれる。それらのものま で、すべて制定または改廃の請求範囲とすると、通常の税金に関する業務が滞る。業務が多量になり、 このため行政に必要な経費が不足する。かえって住民の利益を害する。そこで、地方自治法12条1項 は、条例の制定または改廃請求の対象から、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料などの 徴収に関するものを除外している。
オ×
都道府県は、市町村を統括する地方自治体である。各市町村の「住民につき、住民たる地位に関する正確な記録(生年月日、住所、病院通院歴、海外渡航歴等)を常に整備しておかなければならない」とすると、市町村より対象範囲が広いため、膨大な情報を処理しなければならないことになる。行政の効率的運営に著しい支障が生じる。かえって、住民の利益に反する。そこで、地方自治法13条の2は、「別に法律の定めるところにより(住民基本台帳法等)、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録」は、都道府県ではなく市町村が常に装備することとしている。
市町村の区域内に住んでいる者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民といえる。そこで、地方自治法10条1項は、「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする」と、「住民」を規定している。
イ×
普通地方公共団体の選挙に参与する権利とは、地方公共団体の選挙における選挙権および被選挙権をいう。憲法には、日本国籍を有しない外国人の選挙に参与する権利を認めた規定はない。国民主権(憲1条)から日本国籍を有する者のみ認められるべきである。そこで、地方自治法11条は、「普通地方公共団体の選挙に参与する権利」を「日本国民たる地方公共団体の住民」と、限定している。
ウ○
地方自治とは、日本の地域社会において、住民によって民主的な行政を行うことをいう。住民のための行政である以上、住民は、その役務を享受する権利とともに権利の裏面である義務を負うべきである。そこで、地方自治法10条2項は、「法律の定める所により、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う」としている。
エ×
住民による民主的行政という点からは、「その属する普通地方公共団体のすべての条例について、内容 にかかわらず、制定または改廃を請求する権利を有する」とするのが筋である。しかし、条例には日常 の運営に関する地方税の手数料、使用料等の税金や手続き的な内容のものも含まれる。それらのものま で、すべて制定または改廃の請求範囲とすると、通常の税金に関する業務が滞る。業務が多量になり、 このため行政に必要な経費が不足する。かえって住民の利益を害する。そこで、地方自治法12条1項 は、条例の制定または改廃請求の対象から、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料などの 徴収に関するものを除外している。
オ×
都道府県は、市町村を統括する地方自治体である。各市町村の「住民につき、住民たる地位に関する正確な記録(生年月日、住所、病院通院歴、海外渡航歴等)を常に整備しておかなければならない」とすると、市町村より対象範囲が広いため、膨大な情報を処理しなければならないことになる。行政の効率的運営に著しい支障が生じる。かえって、住民の利益に反する。そこで、地方自治法13条の2は、「別に法律の定めるところにより(住民基本台帳法等)、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録」は、都道府県ではなく市町村が常に装備することとしている。
行政書士試験 令和2年度
- 問3 令和2年 憲法
- 問4 令和2年 憲法
- 問6 令和2年 憲法
- 問7 令和2年 憲法
- 問8 令和2年 行政法
- 問9 令和2年 行政法
- 問10 令和2年 行政法
- 問11 令和2年 行政法
- 問12 令和2年 行政法
- 問13 令和2年 行政法
- 問14 令和2年 行政法
- 問15 令和2年 行政法
- 問16 令和2年 行政法
- 問17 令和2年 行政法
- 問18 令和2年 行政法
- 問19 令和2年 行政法
- 問20 令和2年 行政法
- 問21 令和2年 行政法
- 問22 令和2年 行政法
- 問23 令和2年 行政法
- 問24 令和2年 行政法
- 問25 令和2年 行政法
- 問26 令和2年 行政法
- 問27 令和2年 民法
- 問28 令和2年 民法
- 問29 令和2年 民法
- 問30 令和2年 民法
- 問31 令和2年 民法
- 問32 令和2年 民法
- 問33 令和2年 民法
- 問34 令和2年 民法
- 問35 令和2年 民法
- 問36 令和2年 商法
- 問37 令和2年 商法
- 問38 令和2年 商法
- 問39 令和2年 商法
- 問40 令和2年 商法
- 問41 令和2年 多肢選択式 憲法
- 問42 令和2年 多肢選択式 行政法
- 問43 令和2年 多肢選択式 行政法
年度別過去問