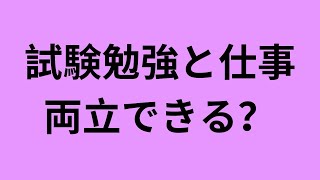ご登録いただくと、続きから問題を
再開する事が出来ます
令和2年 – 問29 – 行政書士 民法
問題29 根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。
1 被担保債権の範囲は、確定した元本および元本確定後の利息その他の定期金の 2年分である。
2 元本確定前においては、被担保債権の範囲を変更することができるが、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を得た上で、その旨の登記をしなければ、変更がなかったものとみなされる。
3 元本確定期日は、当事者の合意のみで変更後の期日を 5 年以内の期日とする限りで変更することができるが、変更前の期日より前に変更の登記をしなければ、変更前の期日に元本が確定する。
4 元本確定前に根抵当権者から被担保債権を譲り受けた者は、その債権について根抵当権を行使することができないが、元本確定前に被担保債務の免責的債務引受があった場合には、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができる。
5 根抵当権設定者は、元本確定後においては、根抵当権の極度額の一切の減額を請求することはできない。
正解3〇×
〔2-29〕
解説
1×
根抵当権は、被担保債権額が極度額の範囲に限定される。後順位抵当権者が、抵当目的物の残存価値を把握できるためである。したがって、通常の抵当権のように、被担保債権の範囲を、確定した元本、利息その他の定期金の2年分に限定する必要がない。よって、肢は誤り。
<条文> 398条の3・1項
<判例> -
2×
根抵当権の被担保債権の範囲や債務者を変更することは、後順位抵当権者やその他の第三者の権利を害するので、承諾が必要ないか。しかし、極度額を変更されない限り、後順位抵当権者や、その他の第三者の利益を害しない。よって、肢は誤り。
<条文> 398条の4・2項
<判例> -
3○
根抵当権の元本確定期日は、当事者の合意で変更できる。変更した日から5年以内である。他方、従前の確定期日はすでに登記されている。もし、従前の確定期日がおとずれる前に、変更後の確定期日を登記しないと、登記を信頼した第三者の利益を害する。したがって、登記が変更されなければ、従前の確定期日が適用される。よって、肢は正しい。 <条文> 398条の6・1項・3項・4項
<判例> -
4×
継続的に発生・消滅を繰り返す債権について、普通抵当権だと別の被担保債権に流用できない。抵当権再設定の手間を省くため、根抵当権は、極度額という一定の範囲内で一括して担保の目的物とする。元本確定前は、被担保債権の範囲に属する債務が譲渡されたり、債務の引受けがされても、随伴性はない。根抵当権者は、引受人の債務について根抵当権を行使できない。よって、肢は誤り。
<条文> 398条の7・2項
<判例> -
5×
根抵当権は、元本が確定すれば、極度額の範囲で権利を行使できるため、普通抵当権と変わらない。そこで、普通抵当権より不利にならないように、根抵当権設定者は、元本の確定後、その極度額を、普通抵当権の被担保債権(注)の限度にまで減額請求できる。よって、肢は誤り。 (注)元本と今後2年間に生ずべき利息その他の定期金および債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額である。
<条文> 398条の21、375条
<判例> -
根抵当権は、被担保債権額が極度額の範囲に限定される。後順位抵当権者が、抵当目的物の残存価値を把握できるためである。したがって、通常の抵当権のように、被担保債権の範囲を、確定した元本、利息その他の定期金の2年分に限定する必要がない。よって、肢は誤り。
<条文> 398条の3・1項
<判例> -
2×
根抵当権の被担保債権の範囲や債務者を変更することは、後順位抵当権者やその他の第三者の権利を害するので、承諾が必要ないか。しかし、極度額を変更されない限り、後順位抵当権者や、その他の第三者の利益を害しない。よって、肢は誤り。
<条文> 398条の4・2項
<判例> -
3○
根抵当権の元本確定期日は、当事者の合意で変更できる。変更した日から5年以内である。他方、従前の確定期日はすでに登記されている。もし、従前の確定期日がおとずれる前に、変更後の確定期日を登記しないと、登記を信頼した第三者の利益を害する。したがって、登記が変更されなければ、従前の確定期日が適用される。よって、肢は正しい。 <条文> 398条の6・1項・3項・4項
<判例> -
4×
継続的に発生・消滅を繰り返す債権について、普通抵当権だと別の被担保債権に流用できない。抵当権再設定の手間を省くため、根抵当権は、極度額という一定の範囲内で一括して担保の目的物とする。元本確定前は、被担保債権の範囲に属する債務が譲渡されたり、債務の引受けがされても、随伴性はない。根抵当権者は、引受人の債務について根抵当権を行使できない。よって、肢は誤り。
<条文> 398条の7・2項
<判例> -
5×
根抵当権は、元本が確定すれば、極度額の範囲で権利を行使できるため、普通抵当権と変わらない。そこで、普通抵当権より不利にならないように、根抵当権設定者は、元本の確定後、その極度額を、普通抵当権の被担保債権(注)の限度にまで減額請求できる。よって、肢は誤り。 (注)元本と今後2年間に生ずべき利息その他の定期金および債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額である。
<条文> 398条の21、375条
<判例> -
行政書士試験 令和2年度
- 問3 令和2年 憲法
- 問4 令和2年 憲法
- 問6 令和2年 憲法
- 問7 令和2年 憲法
- 問8 令和2年 行政法
- 問9 令和2年 行政法
- 問10 令和2年 行政法
- 問11 令和2年 行政法
- 問12 令和2年 行政法
- 問13 令和2年 行政法
- 問14 令和2年 行政法
- 問15 令和2年 行政法
- 問16 令和2年 行政法
- 問17 令和2年 行政法
- 問18 令和2年 行政法
- 問19 令和2年 行政法
- 問20 令和2年 行政法
- 問21 令和2年 行政法
- 問22 令和2年 行政法
- 問23 令和2年 行政法
- 問24 令和2年 行政法
- 問25 令和2年 行政法
- 問26 令和2年 行政法
- 問27 令和2年 民法
- 問28 令和2年 民法
- 問29 令和2年 民法
- 問30 令和2年 民法
- 問31 令和2年 民法
- 問32 令和2年 民法
- 問33 令和2年 民法
- 問34 令和2年 民法
- 問35 令和2年 民法
- 問36 令和2年 商法
- 問37 令和2年 商法
- 問38 令和2年 商法
- 問39 令和2年 商法
- 問40 令和2年 商法
- 問41 令和2年 多肢選択式 憲法
- 問42 令和2年 多肢選択式 行政法
- 問43 令和2年 多肢選択式 行政法
年度別過去問