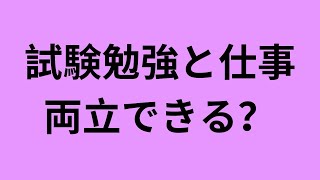ご登録いただくと、続きから問題を
再開する事が出来ます
令和2年 – 問35 – 行政書士 民法
問題35 特別養子制度に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定に照らし、正しいも のの組合せはどれか。
ア 特別養子は、実父母と養父母の間の合意を家庭裁判所に届け出ることによって成立する。
イ 特別養子縁組において養親となる者は、配偶者のある者であって、夫婦いずれもが 20 歳以上であり、かつ、そのいずれかは 25 歳以上でなければならない。
ウ すべての特別養子縁組の成立には、特別養子となる者の同意が要件であり、同意のない特別養子縁組は認められない。
エ 特別養子縁組が成立した場合、実父母及びその血族との親族関係は原則として終了し、特別養子は実父母の相続人となる資格を失う。
オ 特別養子縁組の解消は原則として認められないが、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由がある場合、または、実父母が相当の監護をすることができる場合には、家庭裁判所が離縁の審判を下すことができる。
1 ア・ウ
2 ア・オ
3 イ・ウ
4 イ・エ
5 ウ・オ
正解4〇×
〔2-35〕
解説
ア×
普通養子縁組の成立手続としては、原則として届出で足りる。そこで、特別養子縁組でも、同様に届出で足りないか。しかし、特別養子縁組は15歳未満の者を養子とし、実親子関係を終了させる縁組である。子の福祉向上を図るため、養親となる者の、養育監護に対する責任を負う意思が重要である。したがって、実父母と養父母間の合意を家庭裁判所に届け出るだけでは足りず、家庭裁判所への請求が必要となる。よって、肢は誤り。
<条文> 817条の2
<判例> -
イ○
特別養子縁組は養子の健全な発育と福祉の向上を図るため、実子同様の家族関係を形成する制度である。養親が婚姻していないと子の家族生活に支障が生じるおそれがある。親として精神的・経済的に安定していることが望ましいから、養親夫婦は、ともに20歳以上であり、かつ、そのいずれかは25歳以上でなければならない。よって、肢は正しい。
<条文> 817条の3、817条の4
<判例> -
ウ×
特別養子となる者が15歳未満の場合は、同意は不要である。確かに、特別養子縁組は、普通養子縁組のように意思の合致ではなく、養親となる者の請求により家庭裁判所が成立させる。実親子関係が終了するため、生活環境が変わり、通学等に影響するおそれがあるから、承諾が必要となるとも思える。ただ、子の承諾を要件とすると、かえってその福祉に反するおそれがある(注)。子の生活環境の変化も含め、家庭裁判所が後見的に審査するため、問題はない。したがって、全ての特別養子縁組で同意が必要となるわけではない。よって、肢は誤り。
(注)仮に、子の同意を要すると、実親から脅されるなどして、子が同意せず、手続が進まないおそれがある。
<条文> 817条の5・3項
<判例> -
エ○
普通養子縁組では、実親と子の親族関係は終了しない。他方、特別養子縁組では、実親と子の親族関係を終了させ、子の健全な発育と福祉の向上を図る。実親との親族関係が存続すると、養親と養子が実親子と同様の家族関係を築く上で障害となる場合がある。よって、肢は正しい。
<条文> 817条の9本文
<判例> -
オ×
養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害するなら、終了した実親子関係を復活させればよいから、子を守るため、直ちに特別養子縁組は解消できないか。しかし、そもそも特別養子縁組が成立した背景に、実親による虐待等があった場合、実親子関係を復活させても、問題解決にならない。したがって、実父母が相当の監護ができるという条件も必要である。肢は、養親による虐待等「または」実父母による相当な看護、としている点で誤りである。
<条文> 817条の10・1項
<判例> -
普通養子縁組の成立手続としては、原則として届出で足りる。そこで、特別養子縁組でも、同様に届出で足りないか。しかし、特別養子縁組は15歳未満の者を養子とし、実親子関係を終了させる縁組である。子の福祉向上を図るため、養親となる者の、養育監護に対する責任を負う意思が重要である。したがって、実父母と養父母間の合意を家庭裁判所に届け出るだけでは足りず、家庭裁判所への請求が必要となる。よって、肢は誤り。
<条文> 817条の2
<判例> -
イ○
特別養子縁組は養子の健全な発育と福祉の向上を図るため、実子同様の家族関係を形成する制度である。養親が婚姻していないと子の家族生活に支障が生じるおそれがある。親として精神的・経済的に安定していることが望ましいから、養親夫婦は、ともに20歳以上であり、かつ、そのいずれかは25歳以上でなければならない。よって、肢は正しい。
<条文> 817条の3、817条の4
<判例> -
ウ×
特別養子となる者が15歳未満の場合は、同意は不要である。確かに、特別養子縁組は、普通養子縁組のように意思の合致ではなく、養親となる者の請求により家庭裁判所が成立させる。実親子関係が終了するため、生活環境が変わり、通学等に影響するおそれがあるから、承諾が必要となるとも思える。ただ、子の承諾を要件とすると、かえってその福祉に反するおそれがある(注)。子の生活環境の変化も含め、家庭裁判所が後見的に審査するため、問題はない。したがって、全ての特別養子縁組で同意が必要となるわけではない。よって、肢は誤り。
(注)仮に、子の同意を要すると、実親から脅されるなどして、子が同意せず、手続が進まないおそれがある。
<条文> 817条の5・3項
<判例> -
エ○
普通養子縁組では、実親と子の親族関係は終了しない。他方、特別養子縁組では、実親と子の親族関係を終了させ、子の健全な発育と福祉の向上を図る。実親との親族関係が存続すると、養親と養子が実親子と同様の家族関係を築く上で障害となる場合がある。よって、肢は正しい。
<条文> 817条の9本文
<判例> -
オ×
養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害するなら、終了した実親子関係を復活させればよいから、子を守るため、直ちに特別養子縁組は解消できないか。しかし、そもそも特別養子縁組が成立した背景に、実親による虐待等があった場合、実親子関係を復活させても、問題解決にならない。したがって、実父母が相当の監護ができるという条件も必要である。肢は、養親による虐待等「または」実父母による相当な看護、としている点で誤りである。
<条文> 817条の10・1項
<判例> -
行政書士試験 令和2年度
- 問3 令和2年 憲法
- 問4 令和2年 憲法
- 問6 令和2年 憲法
- 問7 令和2年 憲法
- 問8 令和2年 行政法
- 問9 令和2年 行政法
- 問10 令和2年 行政法
- 問11 令和2年 行政法
- 問12 令和2年 行政法
- 問13 令和2年 行政法
- 問14 令和2年 行政法
- 問15 令和2年 行政法
- 問16 令和2年 行政法
- 問17 令和2年 行政法
- 問18 令和2年 行政法
- 問19 令和2年 行政法
- 問20 令和2年 行政法
- 問21 令和2年 行政法
- 問22 令和2年 行政法
- 問23 令和2年 行政法
- 問24 令和2年 行政法
- 問25 令和2年 行政法
- 問26 令和2年 行政法
- 問27 令和2年 民法
- 問28 令和2年 民法
- 問29 令和2年 民法
- 問30 令和2年 民法
- 問31 令和2年 民法
- 問32 令和2年 民法
- 問33 令和2年 民法
- 問34 令和2年 民法
- 問35 令和2年 民法
- 問36 令和2年 商法
- 問37 令和2年 商法
- 問38 令和2年 商法
- 問39 令和2年 商法
- 問40 令和2年 商法
- 問41 令和2年 多肢選択式 憲法
- 問42 令和2年 多肢選択式 行政法
- 問43 令和2年 多肢選択式 行政法
年度別過去問